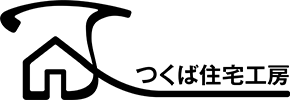江戸に学ぶ、これからの暮らし方
2025.06.27
みなさま、こんにちは。
つくば住宅工房の橋本です。
新しく建てるのではなく、今ある家を、これからの暮らしに合わせて整えていく。そんなリフォーム・リノベーションの道も、いいもんです。建築家と一緒に、わたしたちができることを考えながら、このブログに日々のことを綴っています。
江戸に学ぶ、これからの暮らし方
―循環とつながりの美学-
先日、小江戸・佐原を訪れて
千葉県香取市、佐原の町を歩いてきました。
歴史ある建物が軒を連ね、ゆるやかに流れる水路の音に耳を澄ませながら、ふと「江戸時代の暮らしって、どんな感じだったのだろう」と。
昔の風景に触れたことで、今の暮らしのあり方を問い直したくなった――そんな感覚を、自分なりに言葉にしてみようと思います。
昔の暮らしに目を向けてみると
今はなんでも手に入り、日々の用事も効率的にこなせる時代です。
それでも、どこか「せわしない」「息が詰まる」と感じる瞬間はありませんか。
ふと、江戸の人々の暮らしに目を向けると、不便さの中にある優しさや、自然との距離感、人との関わりの形が、どこか今よりも心に寄り添ってくるように思えたのです。

壊れたら、直して使う
江戸の町には、器が欠けたら修繕し、鍋が壊れたら鋳掛け屋に持ち込んでまた使う、そんな文化が当たり前にありました。
ものを買って終わりではなく、「育てながら使う」という感覚が、暮らしの中に根付いていたように思います。
今のリノベーションの仕事にも、その思想はどこか通じる気がします。
古い建物に触れるとき、ただ“直す”というよりも、その場所に刻まれた時間とやりとりするような感覚があるのです。

“共有”が育てる人とのつながり
長屋の暮らしでは、井戸やかまどを何軒かで共有していたそうです。
便利とは言えなかったかもしれませんが、その不便さが、人と人とを自然に結びつけていたのではないでしょうか。
困ったときはお互いさま、誰かがいてくれる安心感。
そんな“人と関わる場”が、意識しなければ持ちづらい今だからこそ、大切にしたい考え方だと感じます。

自然とともに呼吸する家
江戸の家屋には、土壁、障子、縁側、そして軒の深い庇など、自然と調和する工夫が随所にありました。
冷暖房に頼らず、風や光をうまく取り込む設計。自然を遮断するのではなく、穏やかに受け止めていました。
私たちの時代の建築や暮らしも、もう一度こうした「自然とのつながり」に立ち返ることで、心の余白を取り戻せるような気がしています。

懐かしい未来へ
もちろん、江戸時代そのものに戻ることはできません。
でも、そこにあった価値観――ものを大切にすること、人と関わること、自然と共にあること――には、今の私たちにとって見過ごせないヒントが詰まっていると思います。
懐かしさを手がかりに、これからの暮らしを少しずつ見直していく。
そんな視点を、暮らしの設計や空間づくりの中に織り交ぜていきたいと思いました。